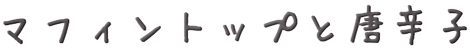イースター(復活祭)といえば、日本と比べ祝日の少ないオーストラリアで働く人々にとっては、
。:.゚ヽ(´∀`。)ノ゚.:。 ゜ やったー!4連休だー! (オーストラリアではイースターの金、土、日、月は祝日です)
と大人は喜びをかみしめ、一方、子どもたちは
。:.゚ヽ(´∀`。)ノ゚.:。 ゜やったー!イースターショーだー!エッグハントだー!
※イースターショー ⇒イースターの時にだけ出現するアミューズメントパークみたいなところ。遊園地と動物とふれあいが楽しめる。詳しくはこちら Sydney Royal Easter Show
ってな感じで、クリスマスやバレンタインと同系列で扱っていいくらいの盛り上がりを見せます。
でも、日本だといまいち盛り上がりに欠けてますよね。
クリスマス、バレンタイン、ハロウィーンはすっかり定番のイベントになったのに、イースターってまだ浸透していない印象。
というわけで、今回は「なぜ日本にイースターが定着しないのか?」と考えてみました。
もくじ
日本にイースターが定着しないのは企業やマスコミの扇動が足りないから?
企業、マスコミがお金になる、と判断しなければ海外のイベントは日本に定着しません。
イースターは商品になるものがクリスマスやハロウィンと違って少ないから、という理由なのかな、と予想します。
イースターで連想されるものといったら、「たまご」「うさぎ」くらいでしょうか。お財布のヒモをゆるめる理由となる「非日常感」が足りませんよね。
クリスマスもハロウィンもバレンタインも、企業が本来の宗教的な意味をうまく排除して消費に促すことを巧みに行っています。イースターでは「商品コンセプト」となり得るものが開発できないのかもしれません。
企業・マスコミの煽りがなければ、新しいコンセプトは定着しません。
イースターが日本に定着しないのはゴールデンウィーク前で消費を避けているから?
1月=正月、2月=バレンタインデー、3月=ひな祭り、4月=新学期……
イベントが目白押しです。
5月に訪れるゴールデンウィークにむけて消費者のお財布のひもは固くなっているのかも。
GWの旅行のために航空券や宿泊費などを事前に支払済みの方の多い時期ですし。
イースターに何をすればいいのかイマイチよくわからないから?
イースターイベントを開催している遊園地やリゾート地、ホテルなども増えてはきているものの、「何をすればいいのかわからない」という方が大多数ではないでしょうか。
- クリスマス=ケンタッキー食べる、プレゼントを贈る
- バレンタインデー=チョコレートを贈る
- ハロウィーン=コスプレ
日本で西洋のイベントが「日本風」にアレンジされて定着してきました。
イースターは「キリストの復活」という、かなり宗教色が強いイベント。
だから企業もマスコミも、「どう騒げばいいか」「何を買えばいいのか」「何を着ればいいのか」といった、具体的なアイデアが見つからないのかもしれません。
消費者も「イースターだからといって何をすればいいのかわからん」といった状態。
とりあえず、ウサギの着ぐるみでも着とく?
日本のイオンではイースター商戦に力を入れているみたい

数年前、イースターの時期に一時帰国をした際、イオンにはたくさんのイースター仕様のお菓子が陳列されていました。


イースターエッグのチョコレートもありました。この「カラフルエッグチョコ」以外はパッと見、イースター関連商品とは気がつかないかも。

「イースター=いつもとは違うパッケージになったお菓子を食べる行事」という雰囲気を感じてしまいましたが、それはそれで楽しそうです。
オーストラリアのイースター情報
最後に、オーストラリアのイースターに関する記事を置いておきます。
興味があれば、のぞいてみてくださいね。