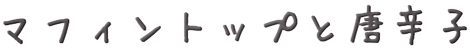シドニーで暮らしていると、毎日の買い物や外食のなかで「プラスチック減らそう」という空気を強く感じます。
スーパーに行ってもレジ袋は出てこないし、カフェでストローを頼めば紙製。
最近は南オーストラリア州で「魚型のしょうゆ容器」禁止というニュースまで飛び込んできました。
「そこまでやる?」と思う一方で、実際に生活していると、規制が「意識高い人だけのもの」ではなく、社会全体のライフスタイルに溶け込んでいるのが面白いところです。
では、なぜオーストラリアはここまでプラスチック規制に熱心なのか?
その背景を解説しつつ、シドニー在住の私の実感も交えて紹介します。
もくじ
オーストラリアの海洋国家としての責任感

オーストラリアは世界最長級の海岸線を持ち、グレートバリアリーフという「世界の宝」も抱える国。
「海を守るのは私たちの責任」という感覚が社会に根付いています。
海鳥の約9割がプラスチックを食べているという調査結果は国内でも大きなニュースになり、子どもたちの環境教育にもよく登場します。
シドニーのビーチを散歩していても「Take 3 for the Sea(海のために3つ拾おう)」というスローガンをよく見かけるほど。
つまり、海と生活が直結している国だからこそ、プラスチック規制が「自然な流れ」として受け入れられやすいのです。
「中国ショック」によるオーストラリア国内の廃棄物処理の限界

かつてはオーストラリアは2016–17年に約125万トンの再生資源(紙・プラ等)を中国へ輸出していました。
オーストラリアの使用済みプラスチックの多くを中国に輸出していましたが、2018年に中国が輸入を禁止。
中国が門を閉めると、国内の選別・再資源化の処理能力が足りず、各地で在庫の山・一時保管・料金値上げといった「リサイクル危機」が発生しました。
ニュースでも連日取り上げられ、自治体や回収業者が緊急対応に追われました。
「出口がないなら、入口を絞る」
これがオーストラリア流の解決策です。
(参照URL:Response to the enforcement of the China National Sword Policy)
オーストラリアの州政府のエコ競争

オーストラリアは連邦制。
環境政策も州単位で進められるため、
「どの州が一番エコ先進か」競争
が起きています。
南オーストラリア州(SA州)は2008年にレジ袋を禁止したパイオニアで、2025年には魚型しょうゆ容器まで規制対象に。
それを「うちも負けてられない」と他州が追随していく形です。
住民としては「州ごとの個性」が出て面白い半面、旅行すると「あれ、この州ではまだプラストローあるんだ」と気づく瞬間も。
国際的なイメージ戦略

観光立国のオーストラリアにとって、「クリーンでサステナブルな国」というイメージは経済資産そのもの。
ビーチの美しさ、自然の豊かさがブランドなので、環境に無頓着だと国際的にマイナスイメージを持たれます。
プラスチック規制は、国際社会に「オーストラリアは環境を大事にする国」とアピールする手段でもあるのです。
オーストラリアのエコバッグ&マイカップ文化

「プラスチック規制」というと堅苦しく聞こえますが、オーストラリアでは生活の中に自然に入り込んでいます。
たとえば、スーパーマーケットのエコバッグ。
シンプル&カラフルなバッグからポップなイラスト入りまで、手頃な価格で購入できるエコバッグは見かけるとついつい欲しくなるアイテム。
旅行者の間では「安い・軽い・実用的」という理由でお土産にも人気。
私も一時帰国のときに家族や友人へのオーストラリア土産に渡しています。
▶オーストラリア土産に迷ったら!エコバッグが喜ばれる理由とおすすめ購入スポット

「使い捨てカップ削減」の流れが強く、マイカップ文化も浸透しています。
その象徴が、メルボルン発祥のリユースカップ 「KeepCup」
2009年に誕生したこのブランドは、「バリスタがそのまま使えるマイカップ」をコンセプトに、世界中に広まりました。
現地のカフェでは、マイカップを持参すると数十セント割引してくれるお店も多く、「エコだから」というより「お得だから」「デザインがかわいいから」という理由で若い世代にも人気です。
規制が不便を生むのではなく、ちょっとした楽しみを生む。これもオーストラリア流の上手なやり方かもしれません。
魚型しょうゆ容器や納豆の箱も禁止に

2025年9月から南オーストラリア州で禁止されるのが「魚型のしょうゆ容器」
小さすぎてリサイクル困難、回収しづらく、海洋ごみに直結するためです。
また、2025年に入り、日本人に身近な食品でいうと四角いプラケース入り納豆も禁止対象となりました。
これらも「プラ容器を減らす」という一環です。
オーストラリアで暮らしていると、「日本の当たり前」が必ずしも世界基準じゃないんだなと気づかされます。
▶オーストラリア、四角い箱に入った納豆が消えた理由(2025年プラスチック規制について)
暮らしの中に馴染むオーストラリアのプラスチック規制

オーストラリアのプラスチック規制は「厳しい」というより「生活に自然に入り込む」もの。
- 海洋国家としての使命感
- 廃棄物政策の転換
- 州ごとの競争
- 国際的なブランド戦略
- ライフスタイルとの親和性
これらの事案が融合して「禁止されても、意外と不便じゃない」社会を作っています。
エコバッグやマイボトルの文化が広がり、暮らしの中でちょっとした楽しみにもなっているのがオーストラリアのプラスチック規制の特徴ではないでしょうか。